
INTERVIEWEE
シュルツァ ライナ
SCHULZER Rainer
東洋大学 情報連携学部情報連携学科 准教授
博士(哲学)。専門分野:哲学、倫理学。2009年ベルリン・フンボルト大学卒業。2018年より現職。
啓蒙思想の時代を生きた哲学者カント。実は親しみやすい人物だった?

──まずは、哲学者カントの人物像と当時の社会情勢について教えていただけますか。
イマヌエル・カントは、あらゆる哲学の分野に多大な影響を及ぼした偉大な哲学者です。彼は、プロイセンの元首都・ケーニヒスベルク(現ロシア領カリーニングラード)で暮らしていました。私生活ではとても社交的で、さまざまな人との交流を好む顔の広い人物として記録が残っています。また、カントといえば「近所の人がカントを見て時計を合わせるほど、毎日きっかり同じ時間に散歩に出かけていた」というエピソードが有名ですが、それは時間に厳しい親友の家を毎日訪れてお茶をしていたから、という裏話があります。几帳面で気難しいという一般的なイメージとは裏腹に、実際には気さくで親しみやすい人物だったのです。
この記事を読んだ人はこちらもオススメ!
近代哲学の祖、カントが唱えた批判主義と道徳とは?【四聖を紐解く②】カントが構想した、平和への道筋。『永遠平和のために』の内容を解説
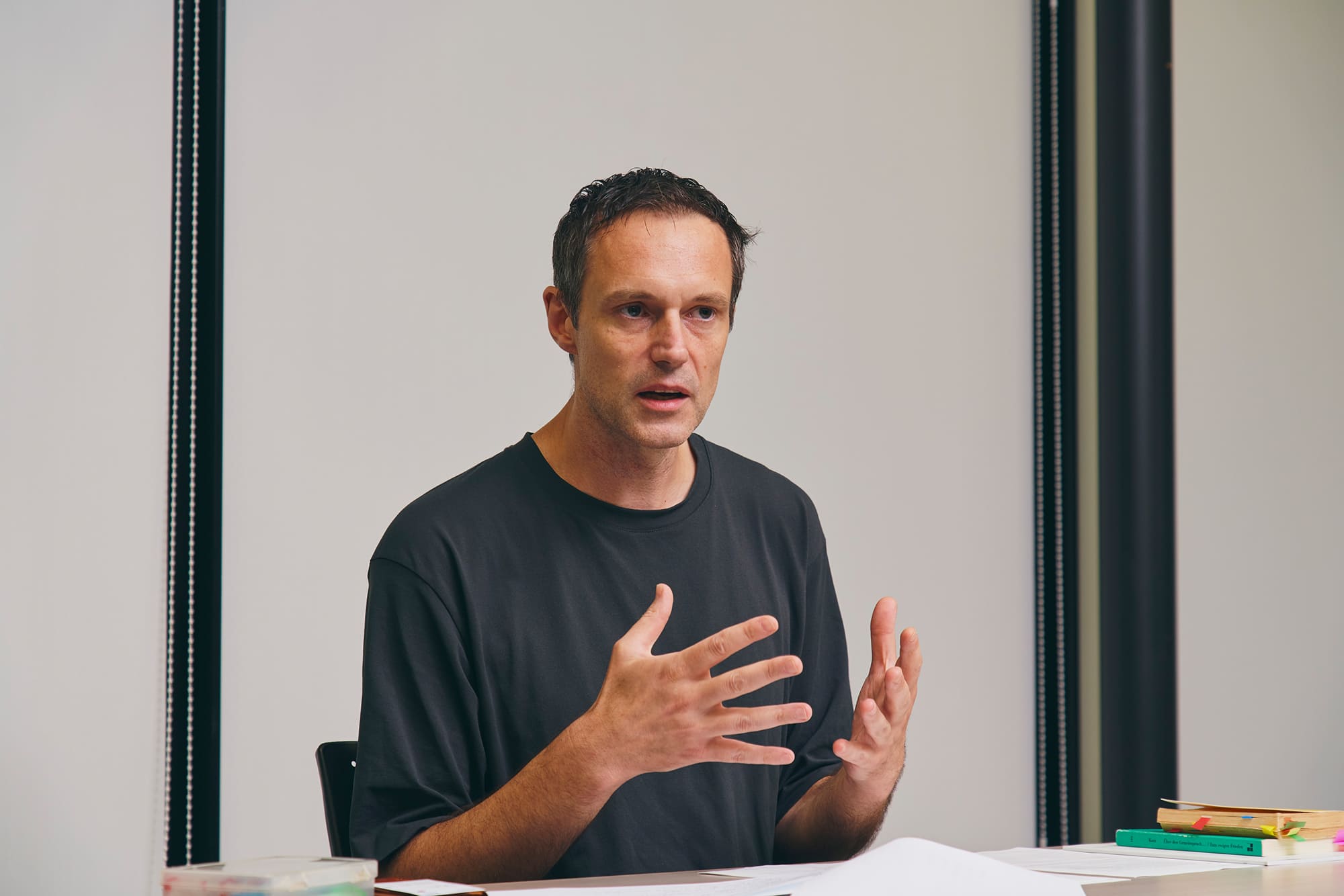
──続いて、『永遠平和のために』の内容について解説いただけますか。
『永遠平和のために』は、国家間の対立を取り除き、永続的な国際平和を築くための具体的な道筋を示した著作です。カントの時代にはまだ国際法という概念自体存在していなかったのですが、『永遠平和のために』の内容には現代の国際法にも通ずる部分が多くあります。
具体的な内容を見ていきましょう。この本は大きく分けて、予備条項と確定条項という二つの部分から成り立っています。予備条項とは、将来的な国際平和の可能性を残すために前提として満たされるべき条件で、全部で6つあります。
一つ目は、「将来の戦争の種を密かに保留して締結された平和条約は、決して平和条約と見なされてはならない」。当時の状況を知らないと少し理解が難しいのですが、この時代は秘密裏に外交を行うことが一般的でした。そのような公共性のない外交は平和の構築を妨げるとカントは考えていたのですね。
二つ目は「独立しているいかなる国家(小国であろうと、大国であろうと、この場合問題ではない)も、継承、交換、買収、または贈与によって、他の国家がこれを取得できるということがあってはならない」。どのような状況であっても、独立している国は物のように扱われるべきではないということです。
三つ目は「常備軍(miles perpetuus)は、時とともに全廃されなければならない」。常備軍は存在自体が国家間の不和を生むため、いずれなくさなければなりません。
四つ目は「国家の対外紛争に関しては、いかなる国債も発行されてはならない」。国が国債を発行できる限り、資金が尽きることはなく戦争がいくらでも可能になってしまうためです。
五つ目は「いかなる国家も他の国の体制や統治に、暴力をもって干渉してはならない」。内政不干渉は、現在の国際法の原則とされていますね。
そして六つ目は、「いかなる国家も、他国との戦争において、将来の平和時における相互の信頼を不可能にしてしまうような行為をしてはならない」。もし戦争が起こってしまった場合においても、そこには限度があるべきだということです。例えば一つの民族を絶滅させることなどはその後の国家間の信頼関係を根本的に破壊してしまうため、戦時下でも決して許されません。こちらも内政不干渉の原則と同じく、戦争犯罪として今日の国際法に採用されている概念です。
以上の6つの予備条項がまず守られない限り、積極的に平和を構築するという次のステップへは進めない、とカントは主張しています。
続いて、3つの確定条項を見てみましょう。先ほどの予備条項を踏まえたうえで、平和を積極的に築き、永続的に維持していくために必要だとカントが考えた条件です。
一つ目は「各国家における市民的体制は、共和的でなければならない」。この「共和的 (republikanisch)」については少し注釈が必要です。今の私たちが「共和制」と言うと、君主制以外の統治形態を指します。一方で、ここでの「共和的」は、国民主権・法治国家・三権分立などの要素を備えた政治形態を指しています。特にカントは、行政権は王室にあってもよいとしつつ、少なくとも立法権は国会にあるべきだと考えていました。そしてこのような性質を持つ国々の間でのみ、平和は維持できるというのが彼の仮説でした。
二つ目は、「国際法は、自由な諸国家の連合制度に基礎を置くべきである」。これはすべての国々が一つの組織としてまとまる「世界政府」のようなイメージではなく、かなりルーズな連合を想定していたようです。カントは、共和的で国民が主権を持つ国では戦争という手段をとる可能性は非常に低いだろうと考えました。戦争をすると、国民自身が多くの犠牲や不利益を被ることになりますからね。戦争に消極的な国がだんだんと増加し、それらがつながって、やがてゆるやかな連合に発展すれば、その中で国際平和が維持できるだろう、と期待したのです。
三つ目は、「世界市民法は、普遍的な友好をもたらす諸条件に制限されなければならない」。これはすべての人がどこへでも旅行をして平和的に滞在できるけれども、そこに無条件に住むことなどはできない、とするものです。当時のヨーロッパ諸国による植民地支配や非ヨーロッパ世界の人々に対する搾取への批判からくるものです。
以上で6つの予備条項と3つの確定条項を紹介しました。カント自身もこれらがすべて簡単に達成できるとは思っておらず、むしろあくまで哲学者として理想的な平和構築の形を示していたわけです。しかしその一方で、条項で分けて書かれているという点はまるで国際規約のようです。実現困難な理想をあえて実際の規約のような形式で提示するという、現実主義者のカントらしいアイロニー(皮肉)も感じられます。
230年前に描かれた理想。何が実現し、何が失敗した?

──カントの政治哲学は、実際の国際社会でどのように実現されたのでしょうか。
二つ目の確定条項の「自由な諸国家の連合制度」の実現に近い出来事として、EUの設立があげられます。EUへの加入には一定の条件が課されていますが、各国の加入・離脱は自由です。また、基本的にすべての加盟国が法治国家かつ人権を守る民主主義を掲げており、平和と共存を主な目的としてつながっています。このように、戦後のヨーロッパはEUによって一つの平和的な文化圏となりました。また、平和的な連合制度があれば他の国々も加入を希望するようになるだろうとカントが予測していた通り、実際に東ヨーロッパの国々なども後からEUに加盟した、または加盟を希望しています。
もう一つ『永遠平和のために』の影響を受けて起こった重要な出来事として、国際連盟の提案と設立があります。第28代アメリカ合衆国大統領のウッドロウ・ウィルソンは、プリンストン大学在学時にカントの政治哲学を勉強し、大きく影響を受けていました。第一次世界大戦の講和に向け、ウィルソンは1918年に「十四か条の平和原則」を発表。その中には国際連盟の提案が含まれており、カントの影響が色濃く見られます。さらに2年後の1920年には、実際に世界初の国際機関として国際連盟が設立されました。しかし、もともとのカントの構想とは異なり、国民主権の国のみならず、ほぼすべての独立国が国際連盟に加入したという点で違いはあります。それは、国際連盟の後身になった国際連合も同様です。国際連盟と国際連合は、一定の形で「自由な諸国家の連合制度」にあたる一方、カントが一つ目の確定条項で表現した国民主権の原則とは一致しません。
──現代の国際情勢を見て、カントはどのように考えると思われますか?
平和を守るには、強い国際法を制定して実行する組織の存在が不可欠だ、というのがカントの根本的な立場です。しかし、現在の国際連合の仕組みには多くの課題が露呈しており、当初期待されたほどの影響力を持てていないのも事実。ですから、国際連合の改革について具体的な提案をするかもしれません。
また、一部の民主主義国家が国際法を軽視して動いていることを悲劇として捉えるのではないでしょうか。先ほども述べた通り、カントは民主主義的な価値観に大きな期待を寄せていました。一度国民主権の国になれば戦争は回避できるだろう、という信頼のようなものがあったのでしょうね。現在、国民の投票によって選ばれた政府が自国優先主義の果てに戦争を開始したり、戦争犯罪を起こしたりしていることを知ったら、カントは大いに悲しみ、批判すると思います。民主主義国家が模範的な行動をとらなければ、カントの描いた理想は崩れてしまいます。
国際平和の実現は、決して容易な道のりではありません。カントの生きた時代から230年が経った今も、それは変わらないように思えます。だからと言って、国際関係においては「強者の権利のみが支配する」という悲観的な見方に陥るべきではありません。カントは、権威主義的な政府であっても自国の戦争をむき出しの暴力としては語らず、必ず「正当な理由」があると主張しようとする、と指摘しています。もし本当に法の力が無意味なら、そのような理屈を並べる必要もないはずです。逆に言えば、たとえ不正国家であっても隣国への侵略行為を正当化しようとすること自体が、「国際政治において法が力を持つこと」の証拠になる――カントはこう指摘したのです。
